この本で得られること・効果
我孫子武丸さんの『殺戮にいたる病』は、
人間の「愛」と「理解」の危うさを、これ以上ないほど鋭く突きつけてくる物語です。
読後には、ただ“ゾッとする”だけで終わりません。
「人を理解するとは、どういうことなのか」
「善悪や愛情の境界は、どこにあるのか」
そんな問いが、静かに胸に残ります。
つまりこの本は――
- “人間の心の奥”を覗きたい人に向けた心理小説
- 日常の見え方が変わるような読書体験
- そして、読み終えてからこそ真価がわかる一冊
として、約30年以上経った今も語り継がれている傑作です。
まず、この小説は“覚悟して”読むべき
正直に言って、読む前に少し覚悟がいります。
血の描写や性的な場面もあり、決して軽い内容ではありません。
けれど、それらは単なる“刺激”ではなく、
人間の内面を描くために不可欠な要素として存在しています。
私は読み終えたあと、
しばらくページを閉じたまま動けませんでした。
言葉にできない違和感と衝撃が、じわじわと押し寄せてくる――
そんな読書体験でした。
あらすじ

物語は、東京・横浜で発生した残酷な連続殺人事件から始まります。
犯人の名は蒲生稔(がもうみのる)。
6件の殺人と1件の未遂を自白し、死刑判決を受けている男です。
一方、その母・雅子は、
「自分の息子が本当にそんなことをするはずがない」と信じたい気持ちと、
「もしかしたら……」という不安の間で揺れ動いています。
さらに、元刑事の樋口は、
被害者のひとりと生前に深い関わりがあり、
罪悪感と再生への想いを抱えながら事件の真相を追いはじめます。
この三人の視点が交錯し、
少しずつ、“ひとつの真実”が浮かび上がっていく――。
しかしその真実は、誰もが想像していたものとはまったく違う方向に向かっていたのです。
“信じていたもの”が崩れていく感覚
この物語のすごさは、
読み進めるうちに自分の中の“確信”が静かに崩れていくところにあります。
登場人物たちの思考や感情が丁寧に描かれるからこそ、
読者はいつの間にか「信じ込んで」しまう。
けれど、その信頼は、やがて足元からすくわれます。
文章の中に潜む“ほんの小さな違和感”。
それが積み重なり、最後の数ページで一気に弾ける。
その瞬間、物語の意味がすべて反転するのです。
私はその一行を読んだとき、
「まさか、そういうことだったのか」と呆然としました。
ページをめくる指が震える感覚――久しぶりに味わいました。
人間の“歪んだ愛”を描く物語
本作には、母と息子、男女、そして夫婦――
さまざまな形の「愛」が登場します。
けれど、そのどれもがどこか少し歪んでいます。
母・雅子は、息子を心配するあまり、
行き過ぎた監視と干渉をしてしまう。
それが母親としての愛情なのか、支配なのか、読むほどに境界があいまいになる。
そして、犯人である稔の愛情も、まるで別の形をとって現れます。
彼にとって「愛」とは、支配であり、所有であり、永遠の融合でもある。
彼の行動は狂気そのものですが、
その奥に潜む“孤独”を想像すると、恐ろしいほど人間的でもあります。
我孫子武丸さんは、
この「愛のゆがみ」を単なるホラーとして描くのではなく、
人間の弱さそのものとして描き出しているのです。
誰におすすめか
『殺戮にいたる病』は、
「人の心の裏側」に興味がある人に強くおすすめです。
たとえば――
- 家族や恋人など、人との距離感に悩むことがある人
- 「愛」と「依存」の違いを考えてみたい人
- 一度読み始めたら止まらない“重厚な物語”を求めている人
- 一気に世界が変わるような衝撃を体験したい人
ただし、残酷な描写や性的なテーマに耐性がない人は注意が必要です。
それでも、読後に得られる“思考の余韻”は、間違いなく深く残ります。
……読み終えたあと、静かな余韻と恐怖が残る。
人間の“善悪の境界”を描いた作品としては、桑垣あゆさんの『レモンと殺人鬼』もおすすめです。
どんなシーンで読みたいか
おすすめは、静かな夜、一人で読むこと。
街の音が少し遠くに聞こえるくらいの時間帯に、
心を落ち着けてページを開いてください。
この物語は、誰かと一緒に読むよりも、
“自分だけが真実を知っていく”という孤独な読書体験の方が似合います。
特に終盤、現実と幻の境界があいまいになるあの感覚――
誰にも邪魔されず、ひとりで味わってほしい。
そして、読み終えた翌日にもう一度、最初のページを開いてみてください。
昨日まで見えていた世界が、まったく違って見えるはずです。
読後に得られる気づきと変化

この作品が心に残るのは、
“恐怖”だけではなく、人間理解への深い問いがあるからです。
母・雅子も、元刑事の樋口も、犯人の稔も、
それぞれに“正しさ”を信じて生きています。
けれど、その「正しさ」が少しずれただけで、
愛が、悲劇へと変わってしまう。
私たちの日常でも、同じことが起こり得るのかもしれません。
人は、相手を“自分の目でしか”見られない。
その限界を、私はこの本を通して思い知らされました。
だからこそ、読後にはこう思うのです。
「理解するとは、支配ではない」
相手を“知ろうとする努力”こそが、本当の愛の形なのかもしれない――と。
私の読書体験:静かな衝撃と再読の夜
読み終えた瞬間、私は本を閉じて深呼吸しました。
あまりの衝撃に、しばらく思考が追いつかなかったのです。
うまく言えないけれど、
この物語には、読んでいるあいだは気づかない「静かな罠」が仕掛けられている気がしました。
気がついた時にはもう、作者の描いた世界の奥底に引きずり込まれていた――そんな感覚です。
ページを閉じたあとも登場人物たちが頭の中に居座り、
「あれは何だったんだろう」「なぜあんなふうに感じたんだろう」と考え続けてしまいました。
この本を読んだ夜、少しだけ「人を信じること」が怖くなりました。
けれど同時に、
“真実を見抜く目”を持ちたいとも強く思いました。
30年経っても色あせない理由
この作品は1992年に発表されたものですが、
驚くほど現代的で、古さをまったく感じません。
スマホもSNSも登場しない時代の話なのに、
登場人物たちの“情報の錯覚”や“認識のズレ”は、
むしろ今の私たちの社会にこそリアルに響きます。
人間の心は、時代を超えて変わらない。
だからこそ、この物語は30年経ってもなお新しいのだと思います。
まとめ:沈黙の余韻を楽しむ一冊
『殺戮にいたる病』は、
読後に静寂が必要になるタイプの本です。
恐ろしいのに、どこか悲しく、
残酷なのに、美しささえ感じる瞬間があります。
読み終えたあと、あなたはきっとこう思うはずです。
「この世界のどこまでが、本当なのだろう」と。
人間の愛、罪、そして理解――
そのすべてを深く考えさせられる、唯一無二の読書体験です。
📘こんな人におすすめ
- 心理描写の深い物語が好きな方
- 一冊で“世界が反転する”ような衝撃を味わいたい方
- 家族や愛、人間の理解について考えたい方
- 一気読みできる緊張感のある作品を探している方
🌙読むのにおすすめのシーン
- 夜、静かな部屋で一人でじっくり
- 雨の日や休日、心が少し沈んでいる時に
- 日常から離れて“人間の深層”に触れたい時に
💭読後に得られる気づき
- 人は「自分の見たい現実」を見ている
- 愛と支配の境界は紙一重
- “理解”は簡単ではないが、それでも人を知ろうとすることが大切
読み終えたあと、あなたの世界の輪郭が静かに揺らぎはじめる。
その瞬間こそが、『殺戮にいたる病』という物語の真の魅力です。
気になった方はこちらからチェックしてみてください。
『殺戮にいたる病』は各ストアで詳しく見られます!
読書の時間が取りにくい方には、耳で楽しめる「Audible」もおすすめです。
通勤中や家事の合間に聴けるので、意外と読書が身近になりますよ。
→ Audibleを30日無料で試してみる
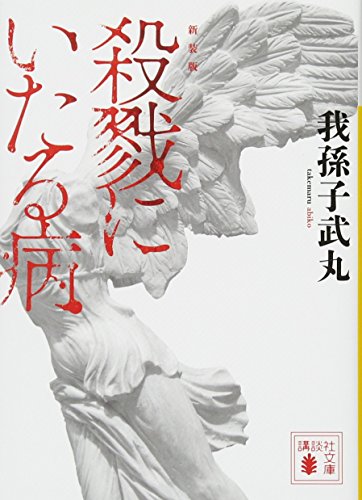

コメント