※このサイトはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を掲載しています。
この本で得られること
『正欲』を読むと、「多様性って本当に受け入れられているの?」という問いが胸に残ります。
理解できない他者を“異常”として排除していないか。
「正しさ」や「まともさ」とは何なのか。
そんな、社会の根っこを静かに揺さぶられる一冊です。
読む前は少し重たい印象があるかもしれません。けれどページを進めるうちに、他人の“ずれ”が自分の中にもあると気づく。
そして、「自分も誰かにとって異物かもしれない」と思えたとき、人を裁く気持ちが少しずつやわらいでいきます。
多様性の時代に投げかけられる違和感
街には「ダイバーシティ」「LGBTQ」「多様性を尊重しよう」という言葉が溢れています。
でも、**“違う人”を本当に受け入れているか?**と問われると、答えに詰まる人も多いはずです。
『正欲』は、まさにこの「言葉の軽さ」に切り込んだ作品です。
「多様性を認める」と口にする社会が、実は「理解できる範囲の多様性」しか許していない。
朝井リョウさんは、そんな現実を残酷なまでにリアルに描き出しています。
あらすじ(ネタバレなし)

物語は、まったく接点のない人たちの視点から描かれます。
検事、専業主婦、不登校の息子、ショッピングモールの販売員、大学生──。
それぞれの生活の中に「生きづらさ」や「違和感」がじわじわと広がっていきます。
ある少年たちのYouTubeチャンネルがきっかけで、物語は次第につながっていきます。
その裏には、“欲”や“性”という人間の根源的なテーマが隠れていました。
彼らの「正しい欲(=正欲)」は、社会から見れば“異常”かもしれない。
けれど、他人を傷つけずに存在するだけなら、それを否定する資格は誰にあるのだろう?
物語はそんな問いを読者に静かに突きつけます。
誰におすすめか
この本は、こんな人にこそ読んでほしい一冊です。
- 「多様性」という言葉にモヤモヤしている人
- SNSの「正しさの暴力」に疲れている人
- 自分の“ズレ”や“生きづらさ”を抱えている人
- 他人との距離感に悩む20〜40代
- 社会問題や現代思想に関心がある読書好き
つまり、「生きにくさ」を感じたことのあるすべての人に響く物語です。
人間関係に疲れた夜、社会のニュースにうんざりした時、静かな部屋でページを開くと心の奥に刺さります。
どんなシーンで読みたいか
『正欲』は、軽い気持ちで読める小説ではありません。
けれど、疲れている時ほど、そっと読んでほしい。
夜、一人きりの時間。
スマホを閉じて、静かにページをめくる。
そんな「他人の声が聞こえない時間」にぴったりです。
また、誰かを「理解できない」と思った瞬間にもおすすめです。
この本を読むと、「理解しようとしなくても、否定しないことはできる」と気づかされます。
“正しい欲”とは何か
タイトルの「正欲」とは、“正しい欲”と書きます。
では、正しい欲とは何でしょうか?
欲望とは、本来、人間が生きるために必要なものです。
けれど、社会の中では“異常”とされる欲も存在します。
『正欲』に登場する人たちは、その「異常」と「普通」の間で苦しんでいます。
他人に理解されない欲を抱えることは、存在そのものを否定されるような痛み。
でも、欲そのものは悪ではない。
誰もが何かしらの「理解されない部分」を抱えて生きているのです。
「多様性」という言葉の暴力
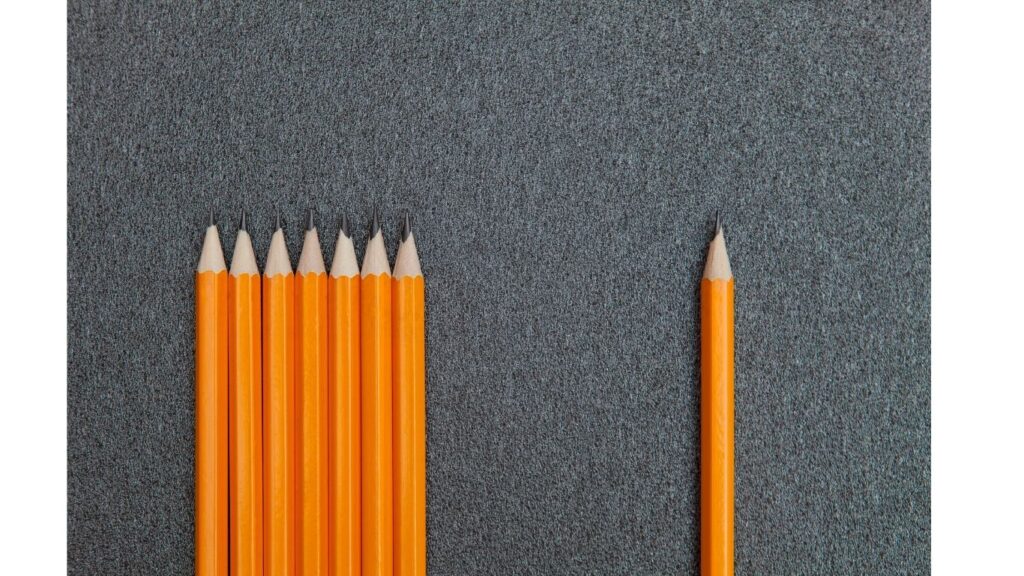
この作品が鋭いのは、“多様性を掲げる社会”そのものが、実は暴力的だという点です。
「理解できる範囲での多様性」だけを受け入れ、
理解できないものは見えないふりをする。
そうして排除された人たちは、
「自分が悪いのか」と自分を責め、社会から消えていく。
朝井リョウさんは、そんな現実を“正面から”描いています。
だからこそ、読みながら胸が苦しくなる。
でも、痛みの中に“真実”があるのです。
登場人物に見る「つながりのかたち」
『正欲』には、いくつもの孤独があります。
学校に行けない少年。
他人と話すのが苦手な販売員。
社会に馴染めない大学生。
どの人物も、孤独を抱えながら“誰かとつながりたい”と願っています。
彼らが求めるのは、理解ではなく「共存」。
ただ、そこにいてくれる人。
「あなたはあなたでいい」と言ってくれる存在。
そしてそれは、どんなに“異常”に見える関係であっても、
彼らにとっては“生きる理由”になるのです。
読後に得られる気づき
『正欲』を読み終えると、心のどこかが静かになります。
派手なカタルシスはありません。
でも、確かに「何かが変わった」と感じるのです。
- 「理解しよう」とするより、「否定しない勇気」を持とう
- “普通”という言葉に惑わされず、自分の感覚を大事にしよう
- “つながり”は数ではなく、深さで決まる
読み終えたあと、「多様性」という言葉を聞くと、
以前とは違う重みを感じるようになります。
たとえば、人にはそれぞれの「生きづらさ」や「痛み」があります。
朝井リョウさんの『正欲』は、それを“理解されない苦しみ”として描きましたが、
同じように社会の不条理や弱者の現実を鋭く描いた作品に、
中山七里さんの『護られなかった者たちへ』があります。
👉 『護られなかった者たちへ』感想記事はこちら
社会と個人の“正義”のすれ違い
この小説のもう一つのテーマは、「正義」です。
検事の寺井啓喜は、法を守る立場として人を裁きます。
しかし同時に、「人を裁くとは何か」を突きつけられる。
罪を犯した人を責めるのは簡単です。
けれど、その“背景”にある苦しみを見ない限り、
社会は同じ過ちを繰り返すのかもしれません。
つまり、「正しいことをする人」が必ずしも“正しい”とは限らないのです。
朝井リョウが描く「リアル」
朝井リョウさんの筆致は、いつも現実的で冷静。
しかし『正欲』では、その冷静さが“社会の冷たさ”そのものとして迫ってきます。
読者は気づくのです。
「自分もまた、“多数派”の側から誰かを排除していたかもしれない」と。
それは決して気持ちのいい気づきではありません。
けれど、その痛みこそが、本当の「多様性」を考える出発点なのです。
この本が教えてくれたこと
『正欲』は、希望の物語ではありません。
けれど、**「絶望の中にもつながりがある」**ことを教えてくれます。
自分の欲を正直に見つめる勇気。
理解できない他者を「存在ごと認める」優しさ。
それは、誰かのためではなく、自分のためでもある。
この物語は、社会に馴染めなかった人たちへの“鎮魂歌”のようでもあり、
同時に、生きることへの“肯定”のようにも感じられます。
まとめ|「正しさ」よりも「誠実さ」を
『正欲』を読むと、世界の見え方が少し変わります。
「正しい人間であろう」とするより、
「誠実な人間であろう」と思えるようになる。
多様性という言葉が軽く聞こえる時代に、
この本は“その言葉の裏側”を教えてくれます。
私たちは皆、どこかで「他人に理解されない何か」を抱えている。
それでも、誰かと繋がれる瞬間がある。
その一瞬こそが、人が生きていく理由なのかもしれません。
『正欲』は、こんな人に読んでほしい
- 他人と比べて苦しいとき
- 「自分は変なのかもしれない」と思う夜
- 世間の「正しさ」に疲れたとき
この本は、“普通”に生きられない人たちの祈りであり、
読む人の心を静かに震わせる傑作です。
📖 『正欲』(朝井リョウ/新潮社)
あなたの中の“正しさ”を、もう一度見つめ直してみませんか。
気になった方はこちらからチェックしてみてください。
『正欲』は、各ストアで詳しく見られます!
読書の時間が取りにくい方には、耳で楽しめる「Audible」もおすすめです。
通勤中や家事の合間に聴けるので、意外と読書が身近になりますよ。
→ Audibleを30日無料で試してみる
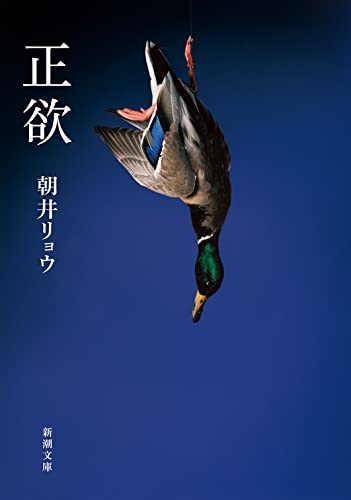

コメント