※このサイトはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を掲載しています。
はじめに:あの静けさと不安のなかで
「パンデミック」——。
その言葉を聞くだけで、あの息苦しい日々を思い出す人も多いでしょう。
マスクで表情を隠し、誰とも距離を詰められず、何かに怯えながら過ごした時間。
一穂ミチさんの短編集『ツミデミック』は、そんな現代の記憶を、ただ記録するだけの物語ではありません。
むしろ、あの時代に生きた「人の心の変化」を描いた文学作品です。
感染したのは、ウイルスではなく“心”だったのかもしれない。
孤独、嫉妬、虚しさ、後悔——。
それぞれの登場人物たちは、まるで見えないウイルスのように広がる感情の中で、
誰かを傷つけたり、誰かに救われたりしながら、生きています。
この本で得られること・効果
『ツミデミック』を読むと、
私たちが「もう終わったこと」として蓋をしていた感情が静かに蘇ります。
・あの頃の不安や孤独を、ようやく言葉にできる
・人の弱さや過ちを、否定せずに受け入れられる
・“生き延びた自分”を、少しだけ誇らしく思える
つまりこの本は、パンデミックという時代を生きたすべての人の“心の回想録”。
過去の出来事を再現するのではなく、
あの時代の「人間らしさ」をすくい取るように描いています。
誰におすすめか
- コロナ禍を経て、どこか心にぽっかり穴が空いたように感じる人
- 「人って、なぜ弱いのに誰かを想うのだろう」と考えたことのある人
- 一穂ミチさんの繊細で静かな筆致に惹かれる読者
- 『スモールワールズ』のように、日常の裂け目を覗くような作品が好きな人
- 人間の闇を描きつつも、最後に微かな希望が欲しい人
特に、「あの頃の自分を、まだうまく言葉にできていない」という人に。
この本は、あなたの中に残っている“未消化の痛み”を、やさしくほどいてくれます。
一穂ミチさんの筆は、“日常のひずみ”を静かに照らすのが本当にうまい。
同じように心に刺さる短編集として話題になった『スモールワールズ』についても、別の記事で紹介しています。
👉 『スモールワールズ』の記事はこちら
一穂ミチが描く“人の弱さ”と“心の温度”
『ツミデミック』というタイトルを見たとき、
多くの人がまず、その響きの強さに心を留めるでしょう。
けれどこの作品で描かれるのは、
「誰かを思いやれなかった後悔」や「自分を守るための嘘」、
あるいは「ほんの小さな無関心」といった、
私たち誰もが抱える“かすかな痛み”です。
一穂ミチさんは、その“心の温度差”を丁寧に描きます。
温度を失った人、ぬくもりを求める人、
そしてようやく自分を赦せるようになる人——。
読んでいるうちに、まるで登場人物たちの呼吸が聞こえるよう。
その心の揺れは、どこかであの頃の私たちと重なります。
各短編が照らす「人間の断片」(ネタバレなし)

この短編集には、六つの物語が収められています。
どれも独立していながら、通底するのは“人の脆さと再生”。
たとえば——
- 閉塞した日常の中で、思いがけず誰かと心が触れる瞬間
- 過去の罪を抱えながらも、赦しを探す人の物語
- 家族という小さな社会の中で、繰り返される選択と誤解
- 死や喪失を経て、それでも誰かを想う力
ひとつひとつの物語が、違う方向から「パンデミックの影」を描いています。
けれど、どの話にも“人は一人では生きられない”という共通の祈りがある。
暗いだけではなく、どこかに温度がある。
絶望の底でさえ、わずかな光が差し込んでいる。
それが一穂ミチさんの物語の美しさです。
読んでいると感じる「あの時の匂い」
この本の凄さは、あの時代の空気を“再現”する力にあります。
ニュースから流れる感染者数、
マスクを外すタイミングを測る沈黙、
人と目が合うだけで生まれる緊張感——。
でも、作者はそれを説明的に書かない。
あくまで登場人物たちの日常の「背景」として、
読者の記憶の底から自然に呼び起こさせる。
読んでいるうちに、
「ああ、あの感覚、たしかにあったな」と思い出すのです。
そしてその記憶は、決して“過去の異常事態”ではなく、
「自分の中にまだ生きている一部」なのだと気づかされます。
どんなシーンで読みたいか
この本は、明るい場所で読むよりも、
少し静かな夜にページをめくるのが似合います。
- 夜更け、スマホを置いて自分と向き合いたいとき
- 誰かに苛立ち、でも本当は優しくなりたいと思うとき
- 「あの頃の自分」をふと振り返りたくなった休日
- 仕事や家庭の中で、孤独を感じた瞬間
どの短編もボリュームがちょうどよく、
疲れた夜に一話ずつ読むのにぴったりです。
読むたびに、
「この登場人物の中にも、自分がいるかもしれない」
そんな不思議な共感が湧き上がります。
読後に訪れる、静かな変化

『ツミデミック』を読み終えたあと、
心の中に残るのは「暗さ」ではありません。
むしろ、「それでも人はやっぱり優しい」という確信のようなものです。
あの時期、私たちは知らず知らずのうちに、
誰かを疑い、誰かに苛立ち、そして誰かを想っていました。
この本は、そのすべてを「人間らしさ」として肯定してくれます。
「罪を抱えても、人は生きていける」
「壊れても、やり直せる」
そう思えるようになるのです。
つまりこの作品は、パンデミックの“総括”ではなく、
人間の再生を描いた、希望の文学です。
一穂ミチという作家の眼差し
一穂ミチさんの文章には、常に「静かな慈しみ」があります。
誰かを断罪するのではなく、ただ見つめ、寄り添う。
読者に“理解”を求めるのではなく、
“共感”をゆっくりと差し出してくれる。
それはまるで、疲れた夜に差し出される温かい飲み物のよう。
現実は何も変わらないけれど、心の中が少しだけ柔らかくなる。
『ツミデミック』は、そんな「人の痛みに寄り添う優しさ」が
ページのすみずみにまで満ちています。
まとめ:あの頃の痛みも、いまを生きる力になる
この短編集には、あの頃の不安や孤独、
そして人と人との小さなつながりが描かれています。
変わってしまった日常の中で、
それでも誰かを想い、立ち上がろうとする人々。
ページを閉じたあとに残るのは、
「生きることは、続いていく」という静かな確信です。
『ツミデミック』は、
喪失の時代を通り抜けたすべての人に贈られる、
優しくも力強いエールのような一冊です。
📖 『ツミデミック』(一穂ミチ/文藝春秋)
時代の痛みをやさしく包み込む、再生の短編集。
あの頃の自分を少しだけ抱きしめたい夜に、ぜひ。
気になった方はこちらからチェックしてみてください。
『ツミデミック』は、各ストアで詳しく見られます!
読書の時間が取りにくい方には、耳で楽しめる「Audible」もおすすめです。
通勤中や家事の合間に聴けるので、意外と読書が身近になりますよ。
→ Audibleを30日無料で試してみる
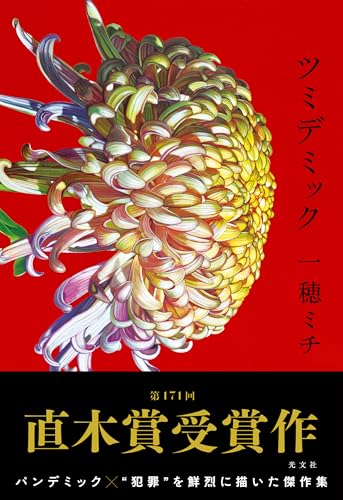

コメント